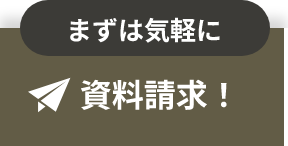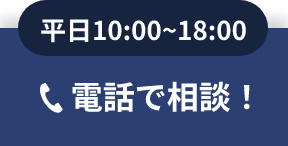それは快楽ではなかった―依存症の現場で見えてきた“生きづらさ”の正体 松本俊彦先生インタビュー (前編)
薬物・アルコール・市販薬オーバードーズを貫く、回復へのヒント
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部は我が国における薬物乱用防止と薬物依存症回復支援に関する研究と診療をけん引してきた。
松本俊彦先生は精神科医として数多くの依存症患者さんの治療を行うとともに、同施設で多くの精神科医の指導も行っており、我が国を代表する依存症治療のトップ名医である。
世界的レベルで活躍されている松本俊彦先生に、FeliMedix(フェリメディックス)株式会社の代表取締役会長で、横浜市立大学医学部肝胆膵消化器病学客員教授、大阪大学大学院医学系研究科招聘教授の小野正文先生が薬物依存症治療のトップ名医の診療の神髄と極意を伺った。

Contents
紹介
氏名:松本 俊彦(まつもと としひこ)先生(医学博士)

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 薬物依存研究部 部長
薬物依存症センター センター長(兼任)
経歴
1993年 佐賀医科大学医学部卒業
1993年 横浜市立大学医学部附属病院研修医
1995年 国立横浜病院精神科シニアレジデント
1996年 神奈川県立精神医療センター 医師
2000年 横浜市立大学医学部附属病院精神科助手
2003年 横浜市立大学医学部精神医学教室医局長
2004年 国立精神・神経センター精神保健研究所 司法精神医学研究部 専門医療・社会復帰研究室長
2007年 同研究所 自殺予防総合対策センター 自殺実態分析室長
2008年 同研究所 薬物依存研究部室長を併任
2010年 独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 自殺予防総合対策センター副センター長/薬物依存研究部 診断治療開発研究室長
2015年 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部 部長
2017年 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院 薬物依存症センター センター長併任
氏名:小野 正文(おの まさふみ)先生(医学博士)

横浜市立大学医学部肝胆膵消化器病学 客員教授
大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授
FeliMedix株式会社 代表取締役会長・創業者・代表医師
経歴
1990年 高知医科大学医学部医学科卒業
1998年 高知医科大学大学院医学研究科修了
1998年 高知医科大学医学部第一内科助手
2000年 ベーラー医科大学感染症内科(米国)リサーチフェロー
2001年 ジョーンズホプキンス大学消化器内科(米国)リサーチフェロー
2015年 高知大学医学部附属病院 准教授
2019年 東京女子医科大学東医療センター内科 准教授
2021年 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授
2024年 大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授
2025年 横浜市立大学医学部肝胆膵消化器病学 客員教授(併任)
意外なきっかけから始まった「依存症専門医」というキャリア
小野先生:
覚醒剤大麻など薬物依存、アルコール依存などの依存症治療の専門家は全国でも数少ないと思うのですが、この分野の専門家になられたきっかけやエピソードがあれば、教えてください。
松本先生:
せっかく素晴らしい質問をして頂いたんですけど、実はきっかけはジャンケンで負けたことなんです(笑)。
神奈川県内で依存症の専門病院があるんですが、前任の先生が辞めちゃったので、代わりに誰かが行かないといけなくなったんです。
依存症って精神科の中でも人気がなくて、みんな行きたがらなかったんですよ。
そこで「神の見えざる手に委ねよう」と、僕がじゃんけんで決めようと提案したら、負けたのが自分で、結局自分が行くことになったんです。
90年代半ばから後半にかけて、いわゆる第三次覚醒剤乱用期という時代がありました。
当時、横浜で診療していた僕は、覚醒剤の使われ方や広がり方が大きく変わっていくのを現場で見ていました。
注射ではなく、ガラスパイプで炙って吸う方法が主流になり、「シャブ」ではなく「S」や「スピード」といった呼び名が使われるようになって、若者の間に一気に広がっていったんです。
神奈川県内の公立高校で、トイレで覚醒剤を使う事件が頻発し、初診日には一度に7、8人の若い患者さんを診ることもありました。
横浜は本当に大変な状況でしたね。
病院の近くには、後に「よまわり先生」と呼ばれる水谷修先生がいて、行き場のない子どもたちを連れて来られることも多く、薬物だけでなく厳しい家庭環境を抱えたケースにも向き合いました。
そうした経験を通じて、依存症治療はとても専門的でありながら、普通の精神科以上に精神科の経験をフル動員しないといけない超応用領域だと気づいて、それからすごく面白くなってきましたね。

快楽ではなく「しんどさから逃れたい」依存症の本質
小野先生:
一般的に依存症は「快楽を求める病気」だと捉えがちですが、先生はよくYouTubeなどで苦痛を緩和したいという動機が本質だとおっしゃっていると思います。
この考え方が生まれた背景や、この視点を持つことが治療にどのような影響を与えるのかを、分かりやすく教えていただけますか。
松本先生:
少なくとも依存症の専門治療に来るレベルになった人たちは、例えばアルコール依存症の人なんかも「酒嫌いだ」って言ってるんですよ。
嫌いだけどやめられないし、自分を責めてる感じ。やってもそんなに気持ちよくない。あとは長く続く苦痛の方で大変な思いをするんです。
だから全然快楽を求めている感じには見えません。
人間って飽きっぽい生き物じゃないですか。どんなに気持ちがいいものでもすぐ飽きますよね。
なのに、なぜ一部の人がお酒や薬物を繰り返すのか。
それは「以前からずっと抱えていたしんどいことが一時的に消えたり楽になるから」手放さなくなるんですよね、普通の自分でいるために。
しんどい仕事や精神疾患、虐待・トラウマの記憶を和らげるためです。
この「苦痛の緩和」の視点を持つと患者さんに優しくなれるんです。
依存症は快楽追求と思い込みやすいですが、実際は楽しい時期はごく短く、長く苦しむ「かわいそうな人たち」だと実感します。
アメリカで80年代から言われていた考え方(自己治療仮説)を、僕が2013年に翻訳本で紹介した頃から、多くの依存症の臨床家に受け入れられ、それ以降、わが国の依存症治療に携わる医療者の質は多少なりとも向上したのではないかと、勝手に自負しています。
甘すぎる飲酒文化と厳しすぎる薬物バッシング
小野先生:
薬物依存とアルコール依存は、依存という点で共通しますが、治療アプローチや社会的なステグマ(偏見)において、どのような違いがありますでしょうか。
特に先生がアルコールを「断トツに危ない薬物」と指摘される理由について、改めて解説をお願いします。
松本先生:
日本ではアルコールに甘く薬物に厳しい特徴があり、社会的スティグマの度合いが大きく違います。
お酒の席では昭和時代にハラスメントが当たり前で、女性がお酌を強いられる文化もありました。
一方、薬物は強いバッシングで全てを失うイメージがあります。
僕自身もお酒を飲みますが、健康被害という点で見ると、内臓をここまでボロボロにする薬物はお酒以外他にほとんどないんですよ。
覚醒剤の方は内臓が比較的元気で、回復後にもレクリエーションでのスポーツなんかでも活躍してたりします。
一方、アルコール依存の方は身体機能の低下が長引き、筋力低下も深刻な方がいます。
法務省のデータや犯罪学研究で、暴力犯罪の加害者の6割から7割が犯行時に飲酒をしています。
児童虐待、ドメスティックバイオレンス、飲酒運転の背景にもアルコール問題が共通認識としてあり、これらを考えると、他者への危害でアルコールが断トツに危ない薬物なんですよね。
ただ、アルコールの規制は本当に難しいです。
みんなが大好きなので、規制するとやっぱり政権が持たなくなる、帝政ロシアが、結局ロシア革命でひっくり返ってしまった。
一番の原因はその前年に皇帝のニコライ2世が禁酒令を出したことがやっぱり影響しているんですよね。
それから、旧ソ連邦の解体もゴルバチョフが反アルコールキャンペーンを80年代の後半にやったんですよね。
ウォッカのアルコール度数の上限を25%に定めたり、酩酊時の暴力を非常に厳罰化したりしたら民意が離れていっちゃったんですよね。それで結局ああいう風に解体してしまった。
みんなが大好きなものは規制できないんですよ。だから、規制に成功しているのは少数派の人が好んでいる薬物なんです。
そういう観点はみんなあまり知られていなくてアルコールはいいけど、薬物は怖いと思われているんだけど、実は依存性とか、内臓障害を考えてみるとアルコールが一番やばいんじゃないかなって気がする。

アルコール性肝障害患者に対する肝臓内科医による支援・治療の工夫は
小野先生:
さらにアルコールについて続けてお伺いします。私は肝臓内科医として多くのアルコール性肝障害、アルコール依存の患者さんを診察、治療してきたのですが、禁酒や減酒を実行してもらうのは容易ではないと感じています。
そこで、特に肝臓内科医はそのような患者さんに対してどのような指導をしたら上手くいくと思いますか?
松本先生:
医者も看護師さんも完璧を求めてしまい、再発すると「ダメだよ」と怒ってしまうんですよね。
断酒・減酒を簡単に言い、自分のお酒問題を棚上げしたり、「もう診ません」と放棄したりするケースも結構ありました。
僕は、「断酒が理想」ですがどうしてもできない人には、最悪の事態を防ぐためにビタミンBやタンパクを補うのも方法だと思います。
英国のクリニックではホームレスのアルコール依存症患者さんにビタミンやたんぱく質豊かな炊き出しの食事を提供していて、それを食べたらお酒を1杯だけ出す。
毎日飲みたい人は毎日来なきゃいけなくなるんですよ。そうすることで肝硬変の発症を抑えられるってことですね。
我々はホームランを打つ必要はなくて、フォアボールでもいいから塁に出るっていう。
ちょっとでもマシなことをやるというのも医者の役割なんじゃないかと思っていますね。
だから、手のつけやすいところから自分を大事にすることを実践していくということも、回り道ではあるけど悪くないのかなと思っています。
内科の先生にも少しだけ優しくなっていただきたいですね。
依存症の人を特別視しない社会へ
小野先生:
依存症は「孤立の病」とも言われていると思いますが、依存症患者が社会で孤立しないために、家族や友人、地域社会といった「人とのつながり(コネクション)」はどのような役割を果たすべきでしょうか。
松本先生:
別に特別に優しくしてほしいとか、腫れ物みたいに扱ってほしいとは思っていないんですよ。
普通の人として、普通に接してほしい、それだけなんです。
実は、お酒や薬物をやめた依存症の人って、外から見ると本当に普通の人なんですよ。
むしろ、社会でしっかり活躍してきた人も多いくらいです。
それなのに、みんなが身構えてしまうのは、これまでの予防啓発のやり方に問題があると思っています。
たとえば昔の「覚醒剤やめますか、人間やめますか」みたいなキャンペーンですよね。
ああいう行き過ぎた啓発は、結果的に差別や偏見を強めてしまう。
実際、ダルクみたいな回復施設ができると、今でも住民の反対運動が起きたりします。
学校の予防教育でも、「ダメ。ゼッタイ。」というお決まりのキャッチコピーを連呼し、その上で乱用防止啓発ポスターを描かせると、みんな薬物依存症の当事者をゾンビやモンスターみたいに描くわけです。
当事者を醜悪に描けば描くほど、コンクールで高く評価されるんです。
大体が、ガイコツみたいな顔で、注射器を持って人を襲う絵です。本人は薬物を表しているつもりでも、結局は当事者のイメージになってしまう。
これを他の病気、たとえばハンセン病やHIV感染症で同じようにやることは許されるのか、って話なんですけど。
こういうことを40年近く続けてきた結果、「昔、覚醒剤やってました」と言った瞬間に、人の見る目が変わってしまう社会になった。
少し遅刻しただけで、「やっぱりだらしない」「またやってるんじゃないか」と思われてしまう。
実名報道もそうです。一度名前が出たら、ネット社会ではデジタルタトゥーとして一生残る。家も借りられない、就職もできない、銀行口座も作れない、といった社会的制裁を何十年も受け続けるんです。
一方で、盗撮みたいな別の依存症では、示談が成立すれば不起訴になって名前も出ず、元の立場に戻れる人もいる。
薬物は示談相手がいないから、起訴されやすい。その違いを、社会全体があまりにも当然のように受け入れている気がします。
結局、今のやり方は人を孤立させているだけなんですよ。
国の啓発も、メディアの報道も、そこが少しでも変わらないと、根本的な解決にはなかなかつながらないと思いますね。
失敗を歓迎し続けることで「もしかしてやめられるかも」を育てる場
小野先生:
スマープは薬物やアルコール依存症の治療を支援するための集団治療プログラムと伺っていますが、プログラムの特徴や重要な点、プログラムへの参加のメリットなどをお聞かせください。
松本先生:
もともと日本の依存症治療は、久里浜医療センターで始まった入院中心の「久里浜方式」がベースでした。
ただ、退院してからの外来プログラムがなく、特に薬物依存症はアルコールのプログラムを無理やり置き換えて使っていたんですね。
でもアルコールはダウナー系、覚醒剤やコカインはアッパー系の薬物で、性質がまったく違います。
アッパー系の薬物は、やめること自体は比較的簡単なんだけど、目の前にあると我慢できずにすぐ再発する。
一方、耐性がどんどん上がって、いくら飲んでも離脱症状を抑えきれなくなってしまうから、最終的にはアルコールは飲んでも飲まなくても地獄みたいになって、本人の方から入院を求めてくる。
この違いがあるので、薬物では入院プログラムがうまくいかなかったんです。
そこで外来で続けられるプログラムが必要だ、ということで、覚醒剤などを主な対象にしてスマープを作りました。
結果的に、今ではアルコールにも使われるようになっています。
スマープのメリットは大きく二つあって、一つはマニュアルとワークブックがあるので、短期間の研修でいろんな医療者が提供できること。
依存症は苦手意識を持つ医療者が多いんですが、「これならできる」と思える点は大きいんです。
もう一つは、とてもゆるいプログラムだということ。大事なのは継続であって、最初から完全にやめることを目標にはしていません。
また使っちゃった、でも来たのは偉いよ、というスタンスで、失敗を責めない。だから、まだやめる自信がない人もつながれるし、通う中で減ってきたり、「もしかしてやめられるかも」と思える人だってまれではないんです。
結局、間口を広げて取りこぼさないためのプログラムなんだと思っています。
後半へ続く