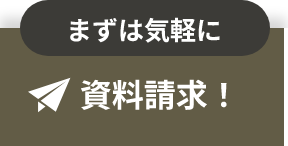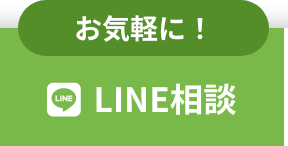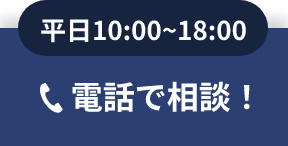【5年先が読める】~脳神経外科トップ名医の神髄に迫る~(後編)
順天堂大学大学院医学研究科脳神経外科学教室は、脳腫瘍治療において日本最高峰の診断・治療レベルを有する日本最大規模の脳神経外科学教室である。
近藤聡英主任教授は、同講座において若手医師たちに診療、研究、教育の指導を行うとともに、医療は疾患によって低下した患者さんの生活の質を改善すべきとして、「必ずしも手術ありきの医療」ではなく患者さんの立場に立った多面的な方法にて疾患の診断・治療を行っている。
世界レベルで活躍されている近藤教授に、FeliMedix(フェリメディックス)株式会社の創業者で、現在は代表医療顧問の小野正文教授(香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座)が、脳神経外科トップ名医の診療の神髄と極意を伺った。

Contents
- 1 紹介
- 2 先進治療について
- 3 医師冥利に尽きるエピソード
- 4 専門性の落とし穴~医師の選び方~
- 5 Q&A
- 5.1 ■医者になると決められたきっかけは?
- 5.2 ■なぜ脳神経外科を選ばれたのですか?
- 5.3 ■頭痛が続いても痛み止めを飲んで治すと人が多いと思いますが、病院に受診した方がいい基準はありますか?
- 5.4 ■パーキンソン病の外科手術というのは、どういうものでしょうか?
- 5.5 ■手術において他の分野、特に消化器分野だと再発しないように大きく取るというのが原則的な考え方だと思いますが、脳は逆ですよね。診断をいかにきちんとするかということがものすごく重要だと思いますが、どのようにお考えですか?
- 5.6 ■人によって脳の使う部分が違うということですが、(脳に腫瘍ができた時に)使う部分の違いが頭の良し悪しに関係するのでしょうか?
- 5.7 ■最近脳にチップを入れると別の言葉を認識できるようになるというものがあるみたいですが、可能なんでしょうか?
- 5.8 ■先生は脳の中に心があると思っていらっしゃいますか。それとも心と脳は別物とお考えですか?
- 5.9 ■先生の座右の銘は?
紹介
氏名:近藤 聡英(こんどう あきひで)

順天堂大学医学部脳神経外科学講座 担当教授(主任教授)
経歴
1999年 順天堂大学医学部卒業
2003年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 助手
2005年 日本脳神経外科学会認定医
2007年 独立行政法人 理化学研究所
2007年 米国ノースウェスタン大学
2010年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 助教
2012年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 准教授
2019年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 先任准教授(助教授)
2020年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 担当教授(主任教授)
氏名:小野 正文(おの まさふみ)

香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授(医学博士)
大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授
東京女子医科大学付属足立医療センター内科 非常勤講師
FeliMedix株式会社 創業者・代表医療顧問
経歴
1990年 高知医科大学医学部医学科卒業
1998年 高知医科大学大学院医学研究科修了
1998年 高知医科大学医学部第一内科助手
2000年 ベーラー医科大学感染症内科(米国)リサーチフェロー
2001年 ジョーンズホプキンス大学消化器内科(米国)リサーチフェロー
2015年 高知大学医学部附属病院 准教授
2019年 東京女子医科大学東医療センター内科 准教授
2021年 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授
2024年 大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授 (併任)
先進治療について
小野先生:
脳腫瘍治療の先進治療ということで何か代表的なものがありましたら教えてください。
近藤先生:
厚生労働省が認めているものと、まだ、なかなか難しいものとで分けて考えなければいけないと思いますが、厚生労働省が認めているものの一つとしては光線力学療法といって、特殊な光当てることによって殺腫瘍作用を持たせるというものがあります。
外科的に取り除くのは難しいようなケースで、これ以上取ったら危ないという時に光感受性物質を内服いただき光を手術中に当ててあげると、もう少し進達度深くまで腫瘍をやっつけることができます。
ほとんど外科的に切除しておいて、残りわずか、もしくは大事な部分に侵入していて物理的にはとれないが、一方で術野に露出しているような腫瘍がある場合には、このような光線力学療法といわれるものが用いられることが多いです。
もう一つの先進医療として用いられているものとしては、神経膠腫の抗がん剤として多く用いられるテモゾロマイドというお薬がありますが、これを大量に使うとか、お薬としてミックスさせて使うような治療が先進医療として提案されているものに入っています。
それ以外のもので一番有名といいますか、実際に何人も患者さんがやっていらっしゃるものとしては、ウイルス療法かなと思います。
これは東京大学医科学研究所のチームが開発したもので、一応上梓されていますがまだ全国には広がっていないタイプの医療です。
このウイルス療法は、ヘルペルウイルスの改変させたものを腫瘍に打ち込むと、まずウイルスが腫瘍そのものをやっつけるんですけども、一方でウイルス感染によって、腫瘍がフラグ化され免疫で排除対象になります。
しまって、そうすると、遠隔にあるような小さい腫瘍も自らの免疫細胞がやっつけてくれるというものです。
小野先生:
ウイルスをがん細胞に感染させることで、それをどんどんやっつけてくれるということですね。
近藤先生:
そうですね。免疫機構を利用したプラスウイルス療法というのが今行われています。
とくに脳には脳血液関門がありますので、全身投与の化学療法というのは実はなかなか病巣に届きにくかったという問題があり、外科医が直接病巣まで行ってから、つまり手術で届けるというやり方が今のところ主流になっています。
ウイルスまで行かなくても、白金製剤を局所注入し、コンベクションといって対流を起こさせて浸透させていく手技がありますが、そういうのも先進のうちの一つとして提案しています。
それ以外にも、まだいくつか発展途上のものはありますが、この分野はなかなかいろんな障害がありますので、臨床応用に進むのはゆっくりですが、少しずつ確実に新しいものが出てくるかなと思います。

医師冥利に尽きるエピソード
小野先生:
近藤先生がこれまでご経験された、脳腫瘍の診断や治療において興味深いエピソードなどあれば教えてください。
近藤先生:
私はお子さんの脳腫瘍を担当するんですが、お医者さん冥利に尽きるエピソードとしては、お子さんが病気になられた後も育っていって、病気の治療頑張っていきますとか、社会人になられましたよ、というふうに報告が返ってくることは大変嬉しいです。
私は大学の教員職も兼ねているので、最近今回、私が手術した患者さん自身が医学生になられて入学してきたというエピソードがありました。
小野先生:
順天堂大学で再会ですか?それは本当に嬉しいですね。
近藤先生:
そういうことがあるのが我々のお仕事の良いとこかなと思います。
もう一つは、なかなかお医者さんと患者さんって友人になりにくいと思うのですが、脳腫瘍というのは生活習慣とか学歴などに影響を受けずに発生してしまうので、色々な職業の方とお知り合いになりやすいんです。
つまり、要職に就かれていてもその病気になられる方もいらっしゃるし、社会的地位の高い方もいらっしゃるし、逆に最終学歴は高校でも一生懸命いろんなことをやられて今は会社の社長さんになられている方とか、そういうところでたくさん出会いがあるというのが、脳腫瘍治療特有の面白いところかもしれません。
大変失礼ですけども、いわゆるがんになるリスクはもう分かっているので、例えば消化器系のがんの方だと、たばこを吸ってお酒が好きで肉体労働していて、いつまでたってもたばこはやめてくれない、常に外来は主従関係というと怒られてしまいますが、医師と患者の関係がずっと保たれていくと思いますが、脳腫瘍の治癒後はそれがなく、友人になりうるんですよね。

専門性の落とし穴~医師の選び方~
小野先生:
脳腫瘍の診断治療で患者さんやご家族が気をつけるようなことが何かありましたら教えてください。
近藤先生:
今、世の中ですごく「専門性」ということが言われています。
しかし、専門性が高ければ高いほど、実は少し足元が見えにくくなっていることが多いんです。
小野先生のやられている活動がすごく尊敬申し上げるところとしては、患者さんが持っている診断と言いましょうか、自分がこうだと信じている診断が必ずしも正しくないということなんです。
これは脳腫瘍では、まだまだあり得ることです。
例えば、ものすごく手術が上手で成績も良く腕がいい先生がいらっしゃって、その先生は脳腫瘍の専門だと言われていたとしても、実は頭蓋底の細かい手術が得意であって、脳実質腫瘍は得意じゃないことも多いんです。
さらに脳腫瘍自体が少ない病気なので、脳腫瘍全般を見るという経験は少ないです。
つまり、どこかにみんな特化していくことによって良い成績を出しています。
ですが、サブスペシャリティの極限を目指せば目指すほど、ミスダイアグノーシス(誤診)につながりやすいところがありますし、治療選択肢も減っていってしまうので、1回はその専門のところを探すのではなくて、意外と普通の広く開いている一般脳外科の先生のご意見を聞いていただくと、「この先生は実はこっちが得意で、もしかしたら違うところの方が得意な先生がいますよ。」という話が聞けるかもしれません。
脳腫瘍という言葉にみんな命の危険を感じておののいてしまうんですが、そうなりすぎないというのをまずご注意いただきたいと思います。
脳腫瘍はある意味助かる病気で、助からない病気の時は必ず専門家が助かりにくいですと、最初に教えてくれます。「こういうことが起こります」といって、専門家であれば必ず5年先が読めます。
5年先のお話をしてくれる先生を選んでいただきたいですね。

Q&A
■医者になると決められたきっかけは?
僕の場合、小児喘息の時期があって、当時あまり良い治療がありませんでした。
減感作といって1回感染させるようなこともやっていましたし、1回風邪をひくとたちまち肺炎になってしまうみたいなこともあったので、この辺は何とかしたいなという思いがベースにあったと思います。
あとは、お医者さんは基本、人に対しておせっかいじゃないとできないんです。
今の医療制度改革だとむしろ逆行の考え方、古いタイプの人間になってしまうかもしれませんが、何かしてあげたいという思いが基本的にはあったというところです。
人を助けてあげたいとかはあまりかっこよくない表現のような気がするので、何か自分ができることがあるんだったらやりたいな、というのがお医者さんになっているきっかけかなと思います。
■なぜ脳神経外科を選ばれたのですか?
医者は完全に向き不向きがあるので、自分で気づきます。
僕は、2次元の画像を3次元に頭で展開するのが得意だったので、外科向きだなと思ったというのはあります。
実は頭の中に左右に2つお水の空間があります。
目の奥、おでこの高さぐらいのところにあるんですが、脳外科の最初の仕事として、水頭症になった時にそこに小さい穴を開けて水を出すことで一時的に脳の圧力を下げるという手技があるんですが、それはほぼ百発百中当たります。
手術でカバーもされてしまうと、普通はどの方向に針を刺すかってなかなか決まりにくいんですけども。。つまりそういうのが得意なんです。
■頭痛が続いても痛み止めを飲んで治すと人が多いと思いますが、病院に受診した方がいい基準はありますか?
基本的に、市販薬で効かなかったら病院に行った方がいいです。
予備知識的な話をすると、毎朝、頭が痛くて目が覚める時は病院に行った方がいいです。
人間の頭の中には、脳みそと脳脊髄液、さっきお話ししたお水の空間と、血管床といって脳を栄養している血管があります。
その血管床のボリュームは変化します。
そして、これは血液中の二酸化炭素で規定されています。
我々起きている時は二酸化炭素が比較的吐けている状態、つまり過呼吸のような状況なんですが、眠っている時の呼吸はゆっくりですよね。
そうすると、実はゆっくり血管床が広がっています。
そうすると、何らか物理的なものが頭の中にあると、朝起きた時が一番頭の中の圧力が高くなっているので、その代償が効かないと頭痛になります。
朝、頭が痛くて目が覚めてしまうというのは、だんだん二酸化炭素が溜まってくることで血管床のボリュームが増え頭の中の圧力が高くなった結果の頭痛になっているということです。
なので、本当に頭が痛くてしょうがない人は寝られません。
ちょっとでも起きていてまどろんでいないと、すぐ頭痛になるという現象が起こります。
■パーキンソン病の外科手術というのは、どういうものでしょうか?
パーキンソン病は、ドーパミンの欠乏によって起こります。
本来ドーパミンを出してくれる黒質とか緻密層と言われるところの細胞の活性が下がってくるので、結果的にドーパミンが出てこなくなる。
なので、ドーパミンを単純に補充してあげればパーキンソン症状というのは本質的には改善してくるわけです。
最初のうちはそれでいいんですが、ドーパミンは「過剰」でも「過小」でもダメなので、最初は朝晩の内服だけだった方がいつの間にか1日3回(分3)になって、次が分4になって、一番ひどい人は分8とか、ずっと薬のケースが並んでいるということが起こります。
こういうことを避けていくために、実はその緻密層に直接電気刺激を与えてあげることでドーパミンを放出させるという技術ができています。
正確に電極を埋め込んでジェネレーターで刺激をしてあげることでそのジェネレーターが感知してドーパミンを出してくれる、というのが外科治療です。
外科治療だけでお話申し上げると、薬を飲むのも大変だから腸瘻をつけてしまって持続ポンプで腸に薬を入れる(内服しないでも自動的に薬が入ってくる)という外科治療もあります。
■手術において他の分野、特に消化器分野だと再発しないように大きく取るというのが原則的な考え方だと思いますが、脳は逆ですよね。診断をいかにきちんとするかということがものすごく重要だと思いますが、どのようにお考えですか?
頭は開け直しがすごく大変なので、むしろ最初から最大切除にいけるように準備をするというのが原則的なルールです。
消化器分野と違って、区域切除ぐらいの準備をして入っていくと、頭の場合結構大変なことになってしまうので、ちゃんと半区域切除ぐらいの感じの準備をして入らなければいけないというのが大原則になります。
治癒切除概念と非治癒切除概念という言い方をしますが、基本的な外科学、特に腫瘍性の病変に対する外科学というのは、治癒切除が最も望まれるわけです。
一方で、脳神経外科学分野は治癒切除に至らないということが前提に医療が行われます。
その最大の理由は、機能温存です。
脳には無機能な部分がないという設定になっていますので、結局セーフティマージンをつける(がんの周囲に余裕を付けて切除する)こと自体が悪なんです。
ただし、セーフティマージンをつけることによって治癒率が上がってくる可能性がある場合には若干の拡大切除をするんですが、その拡大切除をしてもいい部分を見定めるのにすごくエネルギーを使います。
人によってもそれぞれ機能分布が違いますので、機能的MRI(ファンクショナルMRI)というものを使ったり、覚醒下手術といって頭を開けた状態で、患者さんに覚醒していただき、電気刺激で一時的に狭い範囲の脳みそを麻痺させると何が起こるかということを調べて、何も起こらないことを確認してから取り始めるということもします。
摘出マージンが一人一人違うというのが一般外科学と全く違います。
■人によって脳の使う部分が違うということですが、(脳に腫瘍ができた時に)使う部分の違いが頭の良し悪しに関係するのでしょうか?
頭の良し悪しの一つの指標でIQというのがあります。
IQも最低でも4つにはブレイクダウンしないといけないです。
言語性、記憶性、認識性というふうに分かれていくんですけど、どこが得意かということは確かに人によって違います。
女性は、記憶を作るときに写真を撮るみたいに映像記憶というのを使って認識するのが得意な方が多いんですが、そういう方は実は言語性の記憶が苦手なんです。
そうすると、言語に関係するところに病気があっても、ほとんど無症状なんです。
何にも困らないんですが、逆に写真を撮ったように覚えている人が空間認識能のところに病気があって、視野に欠損が起こるだけでほとんど生活できなくなってしまいます。
ちょっとお話が脱線しますが、病気が発生したときに、多くの人間のパターン上ここに異常が発生しているからといって、その人にとって困ってないケースもあるので、その場合にはちょっと拡大切除をしても大丈夫なんです。
そうするとさらに生命予後を良くしていくことができます。
やるところとやらないところももちろんありますが、我々大学病院なので多少そういうことに時間とお金をかけられますので、そうやって決めていくということをしています。
腫瘍の部位がその人の優秀さとかを規定しているわけでは必ずしもなくて、相互関係で決まっていきますので、お一人お一人違うというのがお答えになります。
■最近脳にチップを入れると別の言葉を認識できるようになるというものがあるみたいですが、可能なんでしょうか?
これもすごく個人差があるでしょうね。
必ずしも今のチップが第二言語野を覚醒させるかどうかということとはイコールではないと我々としては思っています。
バイリンガルの患者さんとかにご協力いただいてデータを累積させていますが、言語にもよりますね。
中国語と日本語ってかなり近いですし、文字種が多いことに慣れているので言語的な認識機能が、さっきお話しした空間とか図形の認識の方に広がっている傾向にあります。
そうすると、そこの部分に上手にチップが乗るかっていうと多分難しいかなと思います。
残念ながらいわゆるSIMカードを変えるようにはいかないと思います。
それよりも今ははるかにAIの方が進歩しているので、僕が喋ってもすぐに英語になると思います。
そちらの方のご利用をお勧めします。
■先生は脳の中に心があると思っていらっしゃいますか。それとも心と脳は別物とお考えですか?
一応私は脳神経外科医ですので、自分のプレゼンスはやっぱりヒューマニティのキープであると思っているので、私は脳に心があると思っているタイプの人間となります。
■先生の座右の銘は?
脳の分野は進歩が早いので、勉強し続けることが面白いことだと思っています。
ラテン語圏の言葉で、「私は今も勉強している」っていう単語があります。
一応座右の銘としては『私は今も勉強している』にしようかなと思います。
小野先生:
近藤先生、本当に楽しいお話をありがとうございました。
昔習ったこととは全く違っていて、すごく新鮮なお話だったと思います。
弊社では今後も順天堂大学と連携させて頂きながら、患者さまのために高度専門医療のお手伝いが出来るよう「BeMEC(ビーメック)名医紹介サービス」の充実を図っていきたいと考えております。
本日はありがとうございました。