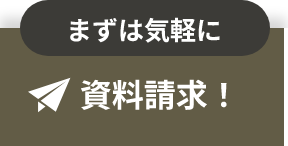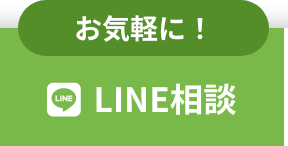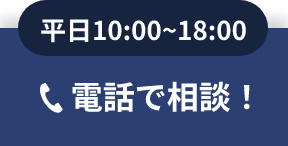【5年先が読める】~脳神経外科トップ名医の神髄に迫る~(前編)
順天堂大学大学院医学研究科脳神経外科学教室は、脳腫瘍治療において日本最高峰の診断・治療レベルを有する日本最大規模の脳神経外科学教室である。
近藤聡英主任教授は、同講座において若手医師たちに診療、研究、教育の指導を行うとともに、医療は疾患によって低下した患者さんの生活の質を改善すべきとして、「必ずしも手術ありきの医療」ではなく患者さんの立場に立った多面的な方法にて疾患の診断・治療を行っている。
世界レベルで活躍されている近藤教授に、FeliMedix(フェリメディックス)株式会社の創業者で、現在は代表医療顧問の小野正文教授(香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座)が、脳神経外科トップ名医の診療の神髄と極意を伺った。

Contents
紹介
氏名:近藤 聡英(こんどう あきひで)

順天堂大学医学部脳神経外科学講座 担当教授(主任教授)
経歴
1999年 順天堂大学医学部卒業
2003年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 助手
2005年 日本脳神経外科学会認定医
2007年 独立行政法人 理化学研究所
2007年 米国ノースウェスタン大学
2010年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 助教
2012年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 准教授
2019年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 先任准教授(助教授)
2020年 順天堂大学医学部脳神経外科学講座 担当教授(主任教授)
氏名:小野 正文(おの まさふみ)

香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授(医学博士)
大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授
東京女子医科大学付属足立医療センター内科 非常勤講師
FeliMedix株式会社 創業者・代表医療顧問
経歴
1990年 高知医科大学医学部医学科卒業
1998年 高知医科大学大学院医学研究科修了
1998年 高知医科大学医学部第一内科助手
2000年 ベーラー医科大学感染症内科(米国)リサーチフェロー
2001年 ジョーンズホプキンス大学消化器内科(米国)リサーチフェロー
2015年 高知大学医学部附属病院 准教授
2019年 東京女子医科大学東医療センター内科 准教授
2021年 香川大学医学部肝・胆・膵内科学先端医療学講座 教授
2024年 大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授 (併任)
脳神経外科として国内最大の大学講座である理由
小野先生:
順天堂大学は脳神経外科の、特に脳腫瘍の手術件数としては日本一ということでお聞きしております。
診療科および近藤先生ご自身として、どのようなことに心がけていらっしゃるかお聞かせください。
近藤先生:
実は、脳腫瘍の手術が看板と言いましょうか、メインなんですけれども、我々としては国内有数な分野を多く有しています。
そのうちの一つは、てんかん外科は、全国一件数が多いことは非営利団体から公表されていますし、少し前ですと脳血管内治療数も1番と言われていました。
現在でも少なくとも5番以内には入ります。
ちょっと特殊なパーキンソンの外科医療というのもありますが、これも国内トップだと思います。
したがって、大学講座の脳神経外科としては国内最大の講座と言えると思います。
具体的には、脳外科の教科書を買ってきて、パラっとページを開くとそのページの手術が明日ある、どこのページを開いてもやれない手術はないというのが僕らの講座です。
先生のご質問にお答えすると、脳という臓器に対して興味のある人間を集めるよう心がけています。
例えば、私はメインで腫瘍を担当しますが、脳腫瘍によって難治性のてんかんみたいなのが起こりえます。
その場合には我々は腫瘍をきっちり治してあげて、その後、すぐにてんかんのチームが引き継げる体制を整えています。
また、腫瘍でも血管障害が絡んでくるケースがあるので、その場合は血管チームの医師たちがよく調べてくれて我々に戻してくれるという順番になっています。
脳という臓器に対応するあらゆるシステムを作り上げているので、結果的に多方面からの目で見ているので漏れがないんです。
他の病院ですと、腫瘍の中でも悪性腫瘍の専門家はいると思います。
しかし、それ以外の専門家がいないと病気の治療に漏れが出来るかもしれないのです。
そこで、私が心がけていることは、なるべく本人の望むサブスペシャリティ(専門性)を伸ばしてあげつつ、他分野とも必ずオーバーラップさせた経験をさせるということです。
脳外科というと救急疾患というイメージが皆さんあると思いますが、救急がやりたくて入ってきた医師がいっぱい脳腫瘍を見ることによって、やっぱり脳腫瘍やりたいということになってきます。
そういう医師は、実は救急疾患に取り組んだ時代に学んだ血管や外傷についてすごくよく知っているので、手術も上手だったり、血行支配に関連した脳腫瘍とかにも対応できるので、一つの分野だけやっている医師たちと比べると最終的な伸びが全然違います。
まず垣根を低くしてみんなでオーバーラップするということを一つの提案としています。
そこに、みんなが話し合いやすいという環境形成を心がけていて、それを逆にご紹介いただいた先生とか、関連の先生たちに広げていくことで、またみんなが集まってきてくれるという構図になるように努力しています。
ですので、心がけていることは、一つの視点だけで見ないように指導しているということです。

まずは「困っていること」を聞く
小野先生:
近藤先生は脳腫瘍の診療の日本トップ名医ですけれども、特に患者さんの診察において特に心がけているという点がありましたら、教えてください。
近藤先生:
一番大事なことは、脳腫瘍って種類が多すぎるんです。
本当は150種類ぐらいあるんですけど、比較的稀な疾患なため、統計を取ると脳腫瘍一つになります。
みんな自分が脳腫瘍だって一回信じてしまうと、そのどれかについて考えず、ただ一つの脳腫瘍になっていってしまうんです。
そこで、私は「脳腫瘍です」といってご紹介された時に、「何が一番お困りですか?」と、まず生活を行っていく上で困っていることを聞くということを一番大事にしています。
それが我々の医療介入で治せるのであればそれは我々の役割がありますし、それが治せないのであれば、逆に我々の存在価値ってあまりないと思います。
また、いわゆる無症状の方、腫瘍が偶然見つかった場合に関しても、おそらくどこかにご本人様が頭を調べてみようかなと思ったきっかけがあるはずなんです。
それをまずなるべく聞き出してあげて、そこから自分ができることを探す、というのが一番心がけていることです。
小野先生:
やはり脳だと、命ということだけではなくて機能異常という点も同時に考えていかなきゃいけない点が他の分野と違いますね。
診察というよりも患者さんとお話をする時間をかなり取られていますか?
近藤先生:
そうですね。
まず、最初に「今回お困りなことはなんですか?」と必ず聞きます。
「特にないです」と言われても、「じゃあなんで頭を検査しようと思われたんですか?」と。
「頭をぶつけたら、たまたま脳腫瘍があるって言われちゃったんです」と言われたとしても、「そんなに簡単に頭をぶつけないですよね?病院に行こうと思うほどぶつけないですよね?」と聞いてみると、家族から「本当に最近よく転んで・・・」という話が出てくると、すると、実はそこに小さな麻痺があるはずなので、その麻痺を探す診察をする。
そういうきっかけをどんどん聞いていくことで、一番問題になっているところ、医療が介入すべきところが分かってきます。
脳腫瘍の診断と生検選択のポイント
小野先生:
脳腫瘍の診断において、病理組織の検査をしないと診断が難しいケースはどのくらいの頻度がありますでしょうか。
近藤先生:
率直に申し上げて脳腫瘍は数が多いので、今はほとんどが分子生物学的診断、つまり遺伝子異常を探すことによってパターン化して、より正確な診断が出せるようになってきています。
したがって、結果的に言うと画像にDNAが映らないものですから、脳腫瘍の診断を確定させるためには必ず組織が必要になります。
診断の確定には、今はほぼ遺伝子検査は必要ということになるので、このご質問の答えとしては100%になります。
小野先生:
生検方法ですが、小さな穴からの針生検と開頭による組織生検があると思いますけども、それぞれのメリット・デメリットのようなものがあれば教えてください。
近藤先生:
針生検がいいのか、比較的大きいオープンバイオプシーに近いような形がいいのかというのを分ける最大のポイントは、手術によってできるだけ切除した方がいい腫瘍の可能性が高い場合には、開頭生検を選んでいます。
一方で、中には手術が無効であったり摘出に適さない部分、それからリンパ腫のようなどちらかというと全身療法の方が効果があると言われているような病気に関しては、積極的に針生検を選んでいます。
なおかつ我々のところは必ず術中迅速病理診断を入れるので、そういう点でも、生検であったとしてもその場で結論を出して手術を終わらせていくという形にしています。
小野先生:
他の分野はどちらかというと侵襲が大きい小さいという考え方の方が先行していると思いますが、それとは違って治療を見据えた方法論という形が、むしろメインということですね。
近藤先生:
脳はやり直しが効かないので、極力先を読んだ状態で取り組んでいるということです。

現在の脳腫瘍治療
小野先生:
脳腫瘍の術後療法として、放射線治療や抗がん剤治療を併用するケースも多いと思いますが、手術だけで腫瘍を取り切ることは難しいものでしょうか。
近藤先生:
そのご質問のお答えには、まず脳腫瘍が、脳実質(脳そのものの病気)か、脳実質外腫瘍(頭蓋骨の中には入っているが脳そのものでない)かに分かれることをご理解頂く必要があります。
神経鞘腫とか髄膜腫のような脳を守る構造物から発生している脳実質外腫瘍に関しては、治癒切除が可能なものも多いです。
つまり、手術だけで治してあげられるケースが多いと申し上げていいと思います。
ただ、それでもセーフティマージン(がんの周囲に余裕を付けて切除する)ですね。
いわゆる安全域を取るためには少し侵襲性が上がってしまいますので、そこのバランスは必要にはなりますが、多くの場合、良性の腫瘍であればわずかに残っていても大きな問題を起こさないことも多いので、そういう点では、手術が実質的な治癒になると言うことはできます。
その先の、セーフティマージンを取ることができないタイプの腫瘍、ほとんどが神経膠腫とかグリオーマと言われるものですけれども、このケースに関しては、残存ありとして治療しなくてはいけません。
残存ありの場合でなおかつ病理組織学的に、ある程度悪性度が高いと判断された場合には放置ができないので、適切な化学療法か放射線療法かが選ばれていくということになりますし、そのコンバインドが治療成績が良いということになれば両方使うということになります。
ですので、脳実質腫瘍であれば実質的には放射線や化学療法が必要というふうにお考えいただきたいと思います。
小野先生:
脳腫瘍の治療において、内視鏡治療というのはどの程度進んでいますでしょうか。
近藤先生:
内視鏡治療は本当に進んでいます。
一番有名なのが経鼻手術といって、鼻からやる手術のものです。
昔はこの経鼻手術でも顕微鏡を使って比較的切開線を大きくしてやっていましたが、今は鼻の鼻腔の大きさで物が全部出入りできるようになっています。
頭蓋底正中部の経鼻手術に関しては全部内視鏡という風にお考えいただいていいと思います。
後半へ続く